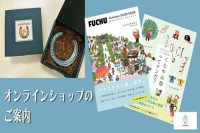季節の変わり目は、体調を崩しやすいタイミングです。
体調を整えるためには、体に良い食事を摂るのが重要です。
この記事では、そんな体に良い食事のポイントについて解説していきます。
季節の変わり目はなぜ体調を崩しやすい?

季節の変わり目は、寒暖差疲労が原因で体調を崩しやすいです。
この寒暖差疲労とは、名前の通り気温の変化によって体が疲れてしまう状態のことを指します。
季節の変わり目のように一日の中で気温差が大きい時期や、室内と外気との差が大きくなる時期に起こりやすく、多くの人が知らないうちに負担を抱えています。
人の体は、自律神経が体温を調整することで外気温と体温のバランスを保っているのです。
しかし、気温の変動が大きいと、この調整に必要なエネルギーが増え自律神経が休む暇なく働き続ける状態になります。
その結果体が消耗し、だるさや頭痛、肩こりなどの不調として現れるのが寒暖差疲労です。
主な症状としては、冷え・肩こり・頭痛・めまい・吐き気・食欲不振・全身のだるさなどが挙げられます。
放置すると、自律神経の乱れが慢性的な不調につながることもあるため早めのケアが大切です。
食事で寒暖差疲労を抑えるためのポイントとは?

寒暖差疲労を防ぐには、日常の食事を見直すことも大切です。
ここでは、毎日の生活に取り入れやすいポイントを紹介します。
規則正しい食事
自律神経は、体温調節を含むさまざまな働きを担っている神経です。
この自律神経は、食事中は交感神経が消化の時間帯には副交感神経が優位になるように切り替わっています。
そのため、1日3食を決まった時間にとるだけでも自律神経のリズムを整えやすくなるのです。
食事の時間がバラバラだったり朝食を抜く生活が続くと、このリズムが乱れて寒暖差疲労につながりやすくなります。
さらに、栄養が偏ると体の機能そのものが低下してしまうため、タンパク質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルをバランスよくとることも重要です。
無理のない範囲で、いつも同じタイミングで食事をする習慣をつけましょう。
旬の食材を食べる
旬の食材は、その季節に必要な栄養を効率よくとれるのが大きなメリットです。
栄養価やうま味が高まるため体調管理に役立ち、寒暖差による疲れが出にくい体づくりをサポートしてくれます。
値段が比較的安いものも多く、続けやすい点も魅力です。
季節ごとの旬の例を挙げると、春はアスパラガスやいちご、夏はトマトや枝豆、秋はきのこ類や柿、冬は白菜やみかんなどがあります。
普段の食卓に少し取り入れるだけでも、免疫力の維持や自律神経の安定につながりやすいです。
体調を整えるために積極的にとりたい食材

体調を整えるために良い食材は何でしょう。
ここからは、体調を整えるために積極的に取りたい食材について解説していきます。
自律神経のリズムを支える食材
日々の体調管理には、自律神経の働きをサポートする栄養が欠かせません。
特に ビタミンB群 を豊富に含む食材は、エネルギー代謝を助け、疲れをため込みにくい体をつくります。
主な食材例
・豚肉
・玄米
・納豆、卵
・レバー
これらを日常的に取り入れることで、身体がリズムよく活動できる状態を維持することが可能です。
体の巡りを整える食材
気温の変化が大きい時期は、血流が乱れやすく、だるさや手足の冷えが生じやすくなります。
ショウガや玉ねぎ のように体を内側から温め、巡りをよくする食材は特に役立ちます。
主な食材例
・ショウガ
・玉ねぎ
・にんにく
・青魚
これらは血流改善に関わる成分を多く含み、身体のこわばりや重だるさを軽減するサポートになるでしょう。
季節の変化に負けないための旬食材
旬の食材は、その季節に必要な栄養を自然と補える点が特長です。
栄養価が高く、味も良く、無理なく日常に取り入れられます。
例:季節ごとの一例
春:アスパラガス、キャベツ
夏:トマト、きゅうり
秋:きのこ類、さつまいも
冬:ねぎ、根菜類
その時期に旬の食材を意識して取り入れることで、季節特有の不調に強い身体づくりが可能です。
免疫機能を支える食材
体調を崩しやすい時期ほど、免疫力を底上げする食材の重要性が高まります。
特に ビタミンC や 抗酸化成分 を豊富に含む食材は、健康維持の基盤になります。
主な食材例
・ブロッコリー
・柑橘類
・パプリカ
・海藻類
体内のストレス負荷を軽減し、健康を保つ助けになるでしょう。
まとめ

季節の変わり目は、自律神経が揺らぎやすく体調を崩しやすい時期です。
刺激物を控え、旬の大根・カブをはじめとした食材を取り入れながら、主食・主菜・副菜をそろえた食事で栄養バランスを整えることが、体調管理の第一歩になります。
無理をせず、温かい料理と旬の栄養で内側から整える食事を心がけましょう。
参考URL冬バテの原因は寒暖差疲労?食事で対策をしよう|大正製薬
【寒暖差疲労対策】季節の変わり目の体調を整える食事のポイント|ぷらす鍼灸整骨院