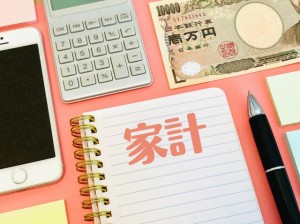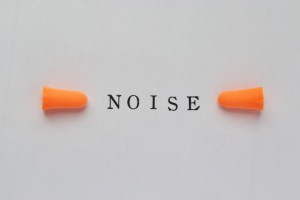引越しを行った時、ご近所さんに挨拶をする機会もあると思います。
この記事では、そんな引越し挨拶に関して解説していきます。
引越し挨拶のタイミングは?

引越し挨拶は、通常「引越しの前日」がベストなタイミングです。
作業でご近所に迷惑をかける可能性があるため、引越し当日に挨拶するよりは『引越し当日はご迷惑おかけします』といった感じで挨拶を事前に済ませておくと良いでしょう。
前日が難しい場合は、搬入作業が始まる前にでも構いませんが、できるだけ早めに挨拶するのがおすすめです。
また、時間帯としては「日中(正午から夕方ごろ)」が最適となります。
寝ていたり何かと忙しい早朝や夜を避けて、日中を選ぶことがマナーです。
これにより、ご近所との関係を円滑に保つことができます。
挨拶の範囲は?

挨拶の適切な範囲は、戸建ての場合は向かいの三軒と両隣の合計5軒程度です。
隣接する家がある場合は裏の家にも挨拶をすることが一般的となります。
一方、マンションやアパートでは上下と左右の隣人へ挨拶します。
ただし、女性の一人暮らしの場合は、自身の安全を考慮して隣人に顔や名前を知らせることに慎重になる必要があるでしょう。
特にマンションの場合は、隣の部屋への挨拶は慎重に行ってください。
旧居への挨拶

旧居の方の引越し挨拶は、引っ越しの1週間以上前に行うのが良いでしょう。
これは、引越し作業によって近隣に迷惑がかかる可能性があることを前もってお知らせするためです。
かかる迷惑としては騒音や通行の妨げ、階段やエレベーターの占有、トラックによる道路の塞ぎなどが挙げられます。
ご迷惑をおかけしますというお知らせと共に、これまでのご近所への感謝の気持ちも忘れずに伝えましょう。
挨拶のタイミングとしては、新居での引越し挨拶と同様に早朝や深夜を避けてください。
相手が不在の場合はどうする?

引越しの挨拶に訪れた際に相手が不在だった場合、2~3回くらい異なる曜日や時間帯に挨拶に訪れてみることが良いでしょう。
それでも不在であれば、手紙を書いてポストや郵便受けに入れておくのがベストです。
手紙の内容としては、下記の通りです。
・簡単な挨拶と名前
・引っ越してきた日付
・何度か挨拶に伺ったが不在だったこと
・引越し当日にお騒がせしてしまうことを詫びる
この内容が入っていれば問題はありません。
また手土産があるのであれば、手紙の中に『ささやかではありますが心ばかりの品をお贈り致します』といった文面を書き記しておくと良いでしょう。
手土産自体は、食べ物を避けてドアノブに引っ掛けておきます。
大家さんへの挨拶は必要?

大家さんへの挨拶は、入居時と退去時の両方で行うのが一般的です。
大家さんが近隣に住んでいる場合や管理人さんがマンション内に常駐している場合は特に重要となります。
入居時に挨拶をすることで、顔を合わせておくことができ、将来何かトラブルや困りごとが生じた際にも相談しやすくなるでしょう。
大家さんや管理人さんが近くにいるかどうかは、事前に不動産会社に確認しておくことが重要です。
挨拶の際には丁寧な態度で、自己紹介や住まいのことを簡潔に伝えることがポイントです。
また、挨拶の際には日時を事前に相手方と調整し、都合の良い時間帯に訪問するようにしましょう。
さらに、大家さんとは別に自治会長さんへの挨拶が必要となる場合もあります。
この場合は、地域の自治会の活動が活発であったり挨拶するのが当たり前と考えている地域性なのであればしておくのが無難でしょう。
手土産はどのようなものを選べば良い?
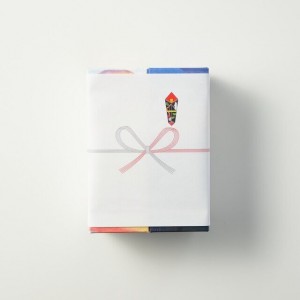
引越し挨拶の際に選ぶ手土産は、消耗品や長持ちする食品が人気です。
たとえば、タオルや洗剤などの生活必需品や、長期保存が可能なお菓子、コーヒーや紅茶のティーバッグが一般的です。
最近では、真空パックされたお米や高品質なティッシュなども好まれます。
ただし、置物や小物類は好みが分かれることから控えることが賢明です。
相手の日常生活で使用するものを選ぶことで、心から喜んでいただけるでしょう。
また、金額の相場としては500円から1,000円程度が妥当です。
高価なものすぎると相手に気を使わせてしまうため、注意が必要です。
おすすめの手土産
ここからは、おすすめの手土産をご紹介していきます。
中川政七商店「彩り豊かな」花ふきん

中川政七商店さんの花ふきんは、高品質でありながら清潔でおしゃれなパッケージが特徴です。
一般的なふきんよりも約4倍の大きさで、食器や台拭きとして幅広く活用できます。
使いやすさと高品質を兼ね備えた、贈られた人が喜ぶふきんです。
丸眞|今治タオル ハンドタオルギフト

タオルはいくつあっても困らない必需品であり、引越しの手土産としても定番です。
中でも丸眞さんの今治タオルハンドタオルギフトは、爽やかなデザインと箱に入ったパッケージで贈り物に最適な商品となっています。
まとめ
ご近所付き合いが薄くなった昨今ですが、やはり隣近所はどのような人が住んでいるのかくらいは把握しておくのがおすすめです。
そのため、引越しの挨拶は行っておくと良いでしょう。
参考URL引越しの挨拶で気をつけることはありますか? | 「日程・挨拶」のマナーについて | 引越しよくあるご質問 |NXの国内引越サービス (nittsu.co.jp)
引越し挨拶のマナー~近隣への挨拶の仕方や手土産の選び方 | 引越し見積もりの引越し侍 (hikkoshizamurai.jp)
「引越し挨拶」のマナーと手土産の選び方|ほどよい関係を大切に。 | キナリノ (kinarino.jp)
引っ越しの挨拶回りは必要?範囲やタイミング、手土産の選び方などのポイントを紹介|引越し見積もり・比較【SUUMO】