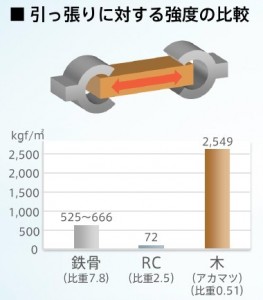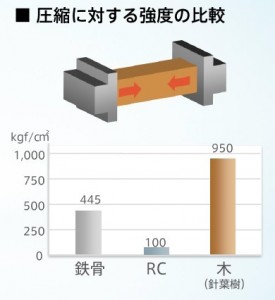お家を購入する際、ローンの組み方としてペアローンというものがあります。この記事では、そんなペアローンについて解説していきます。
ペアローンとは

ペアローンとは、夫婦やパートナーがひとつの物件を購入する際に、それぞれが契約者として住宅ローンを組む方法です。
この方法では、収入に応じて個々の契約者が借入額を決定できるため通常よりも多額の借入が可能です。
また、それぞれが団体信用生命保険に加入することができ、さらには住宅ローン控除を利用することが可能です。
ただし、同じ金融機関でローンを組み、互いに連帯保証人となる必要があります。
また、契約時には手数料や費用がふたり分発生することになります。
ペアローンの例

例えば、5,000万円の家を購入し夫婦でペアローンを組むと仮定してください。
その場合、夫が2,500万円で妻が2,500万円と半分ずつローンを組んでもいいですし、夫が3,000万円で妻が2,000万円と差をつけてローンを組むことも可能です。(収入による)
また、金融機関によってはローンを組む期間に差をつけたり固定金利と変動金利それぞれ選択することもできます。
例えば、夫が35年の固定金利で妻が10年の変動金利などです。
このように、柔軟性の高いローンの組み方ができるため検討の際には一度各金融機関で相談してみると良いでしょう。
ペアローンのメリット

ここからは、ペアローンのメリットについて項目ごとに分けて解説していきます。
借りられる金額が増える
ペアローンは、ふたりで住宅ローンを組むことで通常よりも借入金額が増えるため、手の届かない条件の住まいでも購入しやすくなります。
例えばひとりで500万円の年収の場合、最大で4,330万円までの住宅ローンを組めますが、5,500万円の物件を購入する場合には単独での審査は通りません。
しかし、ペアローンを組むことで個々の収入に応じて借入額を分けることができるため、審査を通過する可能性が高くなります。
これにより、ひとりで組むのではローン審査が難しい物件でも購入できる可能性が高まるでしょう。
住宅ローン控除が夫婦共に適応される
ペアローンを利用すると、共働き世帯の両者が住宅ローン控除の恩恵を受けられます。
住宅ローン控除とは、住宅ローン残高の0.7%が所得税・住民税から控除される制度であり、ペアローンを組む場合は両者の控除額が合算されます。
例えば新築の一般住宅を購入した場合、ふたりの控除額合計は最大で273万円×2人=546万円となります。
このように、ペアローンは控除額が増えるため節税効果を高めることが可能です。
ただし、所得や購入する家の条件によって控除される金額が変わるため、注意が必要です。
ペアローンのデメリット

ペアローンの場合、夫婦でそれぞれのローンを組むため諸経費もそれぞれで必要となります。
そのため、契約時にどちらか片方でローンを組むよりも費用がかさむでしょう。
しかし、ペアローンでは夫婦の両方が住宅ローン控除の恩恵を受けられるため、諸費用の合計と控除で減税される金額の合計を比較した上で検討する必要があります。
ペアローンと似た収入合算とは?

ペアローンでは、複数の要因(勤務先、勤続年数、年収、家族構成、他の借入状況など)を基に銀行が審査を行い、借入可能額を決定します。
契約者の状況によっては、希望金額の住宅ローンを組めない可能性も発生するでしょう。
その際、ローンを組む別の方法として収入合算が考えられます。
収入合算では、夫婦や親子で収入を合算し借入額を増やせる可能性があります。
合算対象者は基本的には同居する配偶者または親子ですが、銀行によって合算可能な金額のルールが異なるため借入機関に確認が必要です。
収入合算のメリット

収入合算の場合、住宅ローン契約の本数は申込者(主債務者)の「1本」になります。
そのため、ペアローンと比較して必要な諸費用(事務手数料、保証料、登記免許税、司法書士への報酬、印紙税など)が抑えられるメリットがあります。
諸費用を節約しつつ借入可能額を増やしたい場合は、収入合算の利用を検討することがおすすめです。
収入合算のデメリット

収入合算の場合、収入合算者は住宅ローン控除の対象外となるというデメリットがあります。
そのため主債務者である申込者だけが控除の恩恵を受けられます。
また、収入合算者は通常団体信用生命保険に加入できないため、万が一の場合に保障を受けることができません。
一部の金融機関では「連生団体信用生命保険」が提供されていますが、取り扱いが限られているため、事前に確認することをおすすめします。
まとめ
ペアローンや収入合算は、借入金額が増えるメリットがあり住宅の購入に有利となりますがその分デメリットもあります。
メリットとデメリットを比較して、ローンの組み方を検討していくようにしましょう。
参考URLペアローンの団体信用生命保険でローンまるごと完済できる?そもそもペアローンと収入合算の違いとは | スーモジャーナル – 住まい・暮らしのニュース・コラムサイト (suumo.jp)
住宅ローンの「収入合算」と「ペアローン」の違いは?メリットや注意点を紹介 | コラム | auじぶん銀行 (jibunbank.co.jp)
そのペアローン待った!元銀行員が仕組みと2つのリスクを完全解説|中古マンションのリノベーションならゼロリノべ (zerorenovation.com)
住宅ローンを収入合算で利用するメリット・デメリット、注意点 | みずほ銀行 (mizuhobank.co.jp)