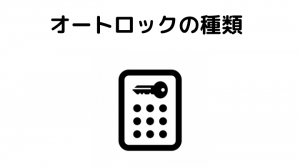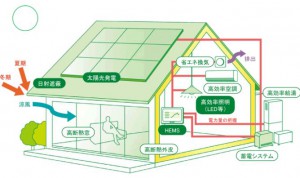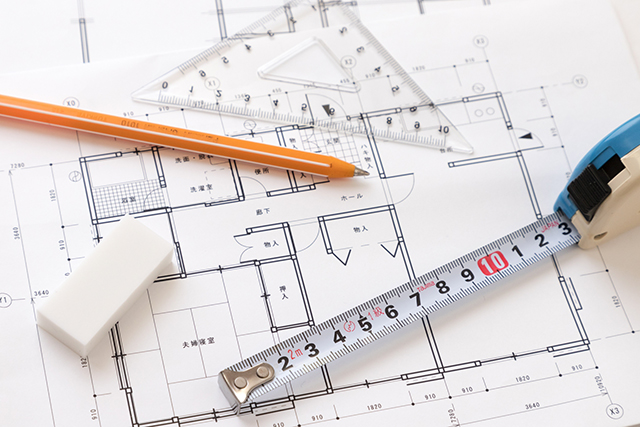最近では、YouTubeの配信やおうち時間の増加で趣味に楽器を始めるという人も増えてきました。そこで気になるのが、騒音です。賃貸であればどうしても周りに迷惑をかけてしまう可能性があります。この記事では、そんな騒音を気にせず思いっきり音を出して楽しめる防音賃貸マンションについてご紹介していきます。
防音マンションの特徴

防音マンションは、防音の機能が完備されている部屋が用意されています。マンションの1室がすべて防音になっているわけではなく、玄関やトイレ、キッチンなどには防音機能が付いていません。防音の部屋ならば楽器の演奏をしたり、カラオケの練習をしたり、オンラインで話しながらゲームをしたりしても問題はありません。
近年では、個人でもYouTubeに投稿して活動している人もいますしゲーム配信をしている人も増えていますから防音マンションの需要はどんどん高まっています。
一般のマンションとの違い
ここからは、一般のマンションと防音のマンションの違いについてご紹介していきます。
壁が違う
壁の構造は、一般のマンションと違い鉄筋コンクリート造の戸境壁の室内側にスタッドという軽い鉄骨を立て空気層を作って吸音材のグラスウールを貼り、一般の石膏ボードよりも比重の重い何枚かの石膏ボード等をスタッドに取り付ける構造の壁になっています。
床が違う
床の構造としては2種類の構造が採用されています。1つ目は、乾式二重床工法です。この工法で作られた床は、床下の空気層が太鼓みたいに音を反響させてしまい逆に防音性を低下させてしまう場合があります。
しかし、防音マンションであればその空気層の中に吸音材のグラスウールがしっかりと敷き詰められている上に床パネルとフローリングの間に石膏ボードや制振ボードなどの音を遮音してくれたり、振動を抑えてくれる材料を使っているのでかなり静かになります。
2つ目は、乾式二重床工法です。この工法は、映画館や音楽ホールなどの音が気になる構造物に採用されています。高い遮音性と防振性能を持ち合わせており、ドラムなど重低音を発するような楽器演奏に対しても効果することが可能です。
天井が違う
防音賃貸マンションは、天井吊りボルトに防振吊り金具を取り付けることで振動を伝えない工法が採用されています。また、防音マンションは吸音性を持っている天井パネルを取り付けることがほとんどです。天井裏のスペースにも吸音性のグラスウールが敷き詰められています。
窓が違う
交通量が多い幹線道路や線路沿いなどの騒音が気になる場所では、二重サッシの窓が一部採用されています。防音マンションでは、二重サッシが基本となっており、高機能の防音マンションでは三重サッシを導入している場合が多いです。二重サッシで40デシベル前後、三重サッシで50デシベル前後の遮音ができます。
ドアが違う
一般のドアは20㎏くらいですが、防音ドアは30㎏以上あります。遮音性は質量に比例していくので、重量を上げることで遮音性を出しているそうです。また、一般のドアはアンダーカットと呼ばれる床下から少し隙間を開ける形になっています。
しかし、これではここから音が漏れてしまいますが、防音ドアの場合音漏れを防ぐためのパッキンが取り付けられているので防音効果が期待できます。
また、高性能な防音マンションであればドアが二重になっており50デシベル前後の遮音ができると言われています。
防音マンションのメリット

防音マンションのメリットは下記3点です。
・楽器やオンラインで話す声以外にも生活音さえ気にならない
・防音だけでなく、断熱性も高くて暖かい
・深夜だろうが早朝だろうが好きな音量で音楽やゲームを楽しめる
自分が出す音以外にも、周りの騒音に悩まされることは多々あるでしょう。しかし、防音マンションであれば周りの騒音も気にすることなく生活することができます。
特に夜勤メインで働いている人や不規則な勤務を行っている人は、世間が活動している時間帯に睡眠を取らなくてはいけない場合が多いですが、防音の部屋があれば静かにゆっくりと睡眠を取ることができます。
防音マンションのデメリット

防音マンションのデメリットは下記3点です。
・壁の厚みや二重ドアなど厚みが増えるので部屋が狭くなる
・地方などだと物件が無い場合がある
・家賃は一般の賃貸より高額
防音マンションは、都市部などであれば見つかるかもしれませんが物件数は少ないです。地方であれば見つけるのがかなり困難でしょう。また、希望の立地に無かったり家賃など予算が合わない場合もあるため防音というメリットを取るために様々な条件を捨てなくてはいけない場合もあります。
まとめ
防音マンションは、自分が発する音も外からの音も気にせずに生活することができます。いつでも好きな音楽や映画を大音量で楽しむことができますし、静かに寝たいという場合にも最高です。周りを気にせず、自分らしく暮らしていきたい人は防音マンションを検討してみてはいかがでしょうか。
参考URL防音賃貸マンションは楽器演奏が24時間可能って本当?実際に行ってたしかめてみた! | 住まいのお役立ち記事 (suumo.jp)
防音マンションとは?一般賃貸物件と防音賃貸物件の違いを徹底解説! | 防音賃貸エンターテイメントマンション・サウンドプルーフ (soundproof.jp)